徳島は山あり海ありのグルメ大国。フィッシュカツを食べてみたい筆者( ![]() .@azusagut )です。
.@azusagut )です。
徳島は阿波踊りが何より有名ですが、実は作陶も行われているのもご存じですか?
それこそ、大谷焼です。
本記事では、大谷焼の
- 歴史
- 特徴
- 資料館・美術館
- 陶器市
についてさくっと、解説していきます。
他の焼き物については↓コチラから。
大谷焼の歴史

大谷焼は徳島県鳴門市大麻町で誕生しました。昔は「大谷村」だったため、「大谷焼」と名付けられています。
大谷焼のおこり
大谷焼は江戸後期の1780年に文右衛門というやきもの技師が、
現在の鳴門大麻町である「大谷村」を訪れ陶器を作成したのがはじまれだと考えられています。
翌年の1781年には藩主である蜂須賀治昭公が村内に「藩窯」を築き、染付磁器の作成が早くも始まりました。

徳島県では初となる染付磁器です
が、残念ながら大谷では原材料の多くを九州からの取り寄せていたことから出費がかさみ、
1784年には一時窯の火は消えてしまいました。



採算が取れなかったのはつらいですね
藩窯から民窯へ


その後、藩窯立ち上げにもかかわった藍商人、賀屋文五郎(笠井惣左衛門とも)が
旅先で信楽焼職人である忠蔵と出会い、大谷村へ連れ帰って雇いました。
彼を中心として村内に「連房式登窯」が作られました。
まさに「藩窯」ではなく、日用品陶器を焼く「民窯」が誕生した瞬間です。
この窯では原材料を地元の萩原や姫田から仕入れるようにし、コストダウンを図りました。
最盛期には十数軒の窯元が存在していたそうですが、現在残っている窯は6軒です。
大谷焼では水甕、藍甕といった比較的大きい陶器の生産が多かったのですが、
特に大正時代あたりから日用陶器の作成も多く行われ、現在の形に落ち着いています。



徳島は昔から藍染が非常に盛んでこの藍甕はとても重用されたそう



2003年には経済産業省の伝統的工芸品に指定されました
大谷焼の特徴


大谷焼の特徴といえば、素朴な風合い。そして「寝ろくろ」という製法です。
大谷の土は鉄分が多く含まれており、ざらっとした風合い、弱い光沢をもっています。



非常に力強いさと素朴な印象を受ける作風です。
そして、大型の陶器を作っている大谷焼ならではの「寝ろくろ」!これは写真を見た方が早いと思います。


職人が作業台の下に寝ころび、ろくろをけって回しています。
とんでもない大きさの甕を焼くため、大谷の登り窯は日本一の大きさとも言われています。
大谷焼に関する資料館


公共のものはありませんが、1軒あります。
大谷焼 陶業会館 梅里窯


こちらのほかでも体験、販売ができる窯元はあります。



ネットでの販売も行っていますよ
大谷焼の陶器市
年に2回「大谷焼の里スプリングフェスタ」と「大谷焼窯まつり」が催されます。
通常より割り引かれた値段で購入できるほか、名陶展も開かれます。



旅行もかねて行ってみては?
大谷焼まとめ
本記事では「【さくっと解説】徳島の藍染と生活を支えた民陶大谷焼の歴史と特徴」について書きました。
徳島では珍しい陶器ですが、藍甕をはじめとして昔から庶民の生活を支えてきた大谷焼。
素朴ながらも力強いうつわを手に取ってみてください。
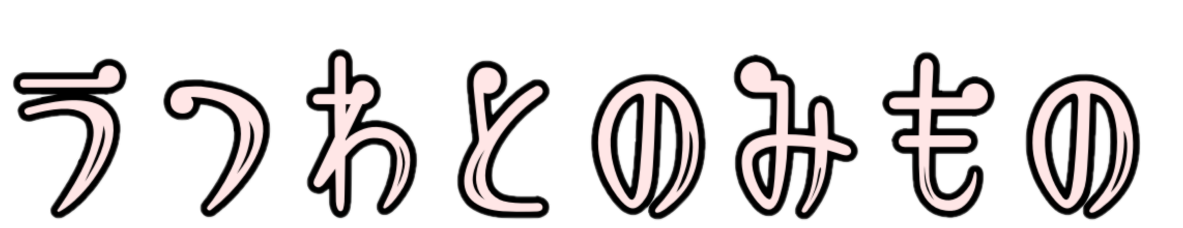


コメント